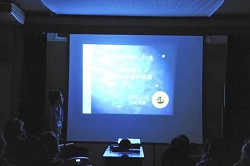第60回井の頭かんさつ会
テーマ: 「井の頭池の生き物つながり」
日時: 2010年6月20日(日) 午前10:00~12:00
場所: 井の頭池
集合: 午前9時45分 井の頭池ボート乗り場前
主催: 井の頭かんさつ会
後援: 東京都西部公園緑地事務所
案内:
田中 利秋(NACS-J自然観察指導員)
大原 正子
高野 丈(NACS-J自然観察指導員)
高久 晴子
佐藤 誠
田中 雅子(NACS-J自然観察指導員)
大橋 博資
上村 肇
協力:
安藤伸良、酒井建樹、竹内隆一、藤森秀一朗、別紙直樹
参加者:26名
レポート
心配された雨雲を皆の執念で吹き飛ばし、梅雨時にしてはまあまあのお天気で観察会はスタートしました。 茶色に濁った井の頭池、そこにどんな生き物達がいるのだろう~参加者達のワクワクした気持ちが伝わってきました。
最初の探索場所はお茶の水池北岸の枝垂れ柳周辺。日ごろ外来魚調査に活躍しているスタッフがチェストウェーダー(胸まである胴長靴)とライフジャケットを着用して池に入り、水中に張り出た柳の根っこの下をサデ網やタモ網でガサガサ~~ すると、網の中には小さなエビ類やハゼ類が何匹も入っているではありませんか! 外来魚調査を始めたころには失われていた光景です。 それらをプラスチックトレイや透明ケースにいれて、皆でじっくり観察。皆初めて観る池の中の小動物に目をぱちくりでした。
次は藤棚の下に移動。、殆どの方たちはそこにあることも気づいていない水中の7つの土管の中の調査です。その土管は直径1m位で、その昔、公園が水生植物を生やそうと設置したらしいのですが、今はオオクチバスの産卵場所になっているため、我々が繁殖抑制活動を行っている場所です。 その土管の中をかき回すと、エビ類、ハゼ類が出てきて、それを網で掬いました。また、後から詳しく観るために底の泥も採取しました。
いよいよ弁天池畔の分園入口前でこの観察会のクライマックスを迎えました。顕微鏡での微細生物の観察です。 参加者たちも、プランクトンネットを使って、陸上からプランクトンの採取。 また、スタッフがいろいろな生き物や、プランクトンの入った池の他の場所の水も予め採取し用意しておきました。 糸のような小さなアカムシを実体顕微鏡で拡大してみると、そこには迫力のある真っ赤なアカムシが~ 肉眼ではただ濁っている池の水も、顕微鏡で100倍にしてみると、なんと美しいクンショウモ(植物プランクトン、緑藻類)の姿が~! 珪藻も藍藻も見えます~ ゾウミジンコやワムシもぴょこぴょこ泳ぎ回っています~
最後に、田中代表が、これらの小さな生き物達が他の生き物に食べられ、さらにその食べた生き物達も別の生き物に食べられて命が繋がっていくこと、そして、誰かが持ち込んだオオクチバスやブルーギルなどの外来生物が増えて、その繋がりがおかしくなったことを解説し、質疑応答も加えて観察会を閉じました。
この観察会は、普段目にすることの出来ない池の中の生き物達を観て、参加者はサプライズの連続だったかもしれません。


(レポート:大原、)